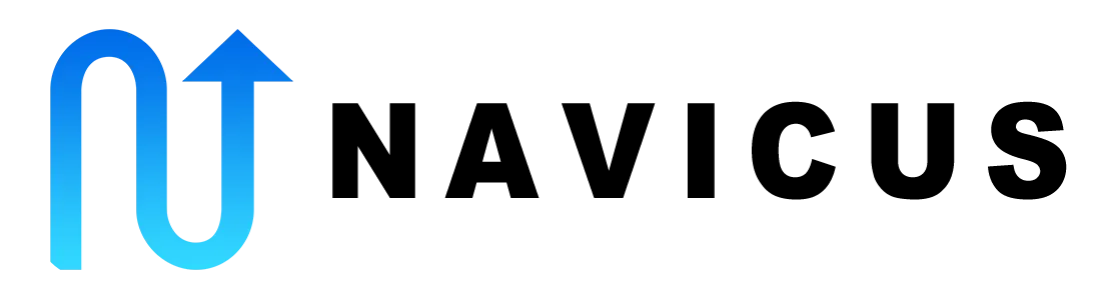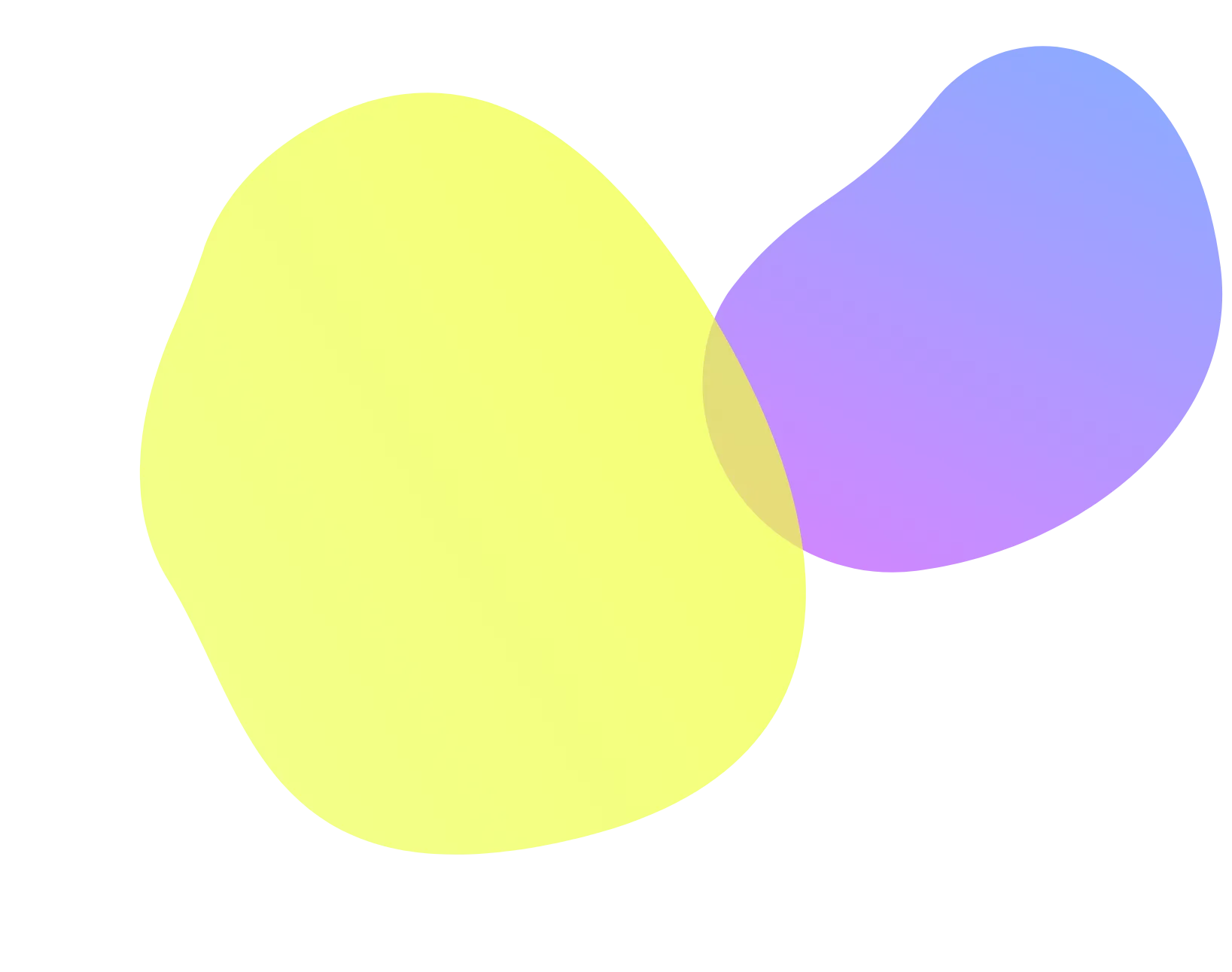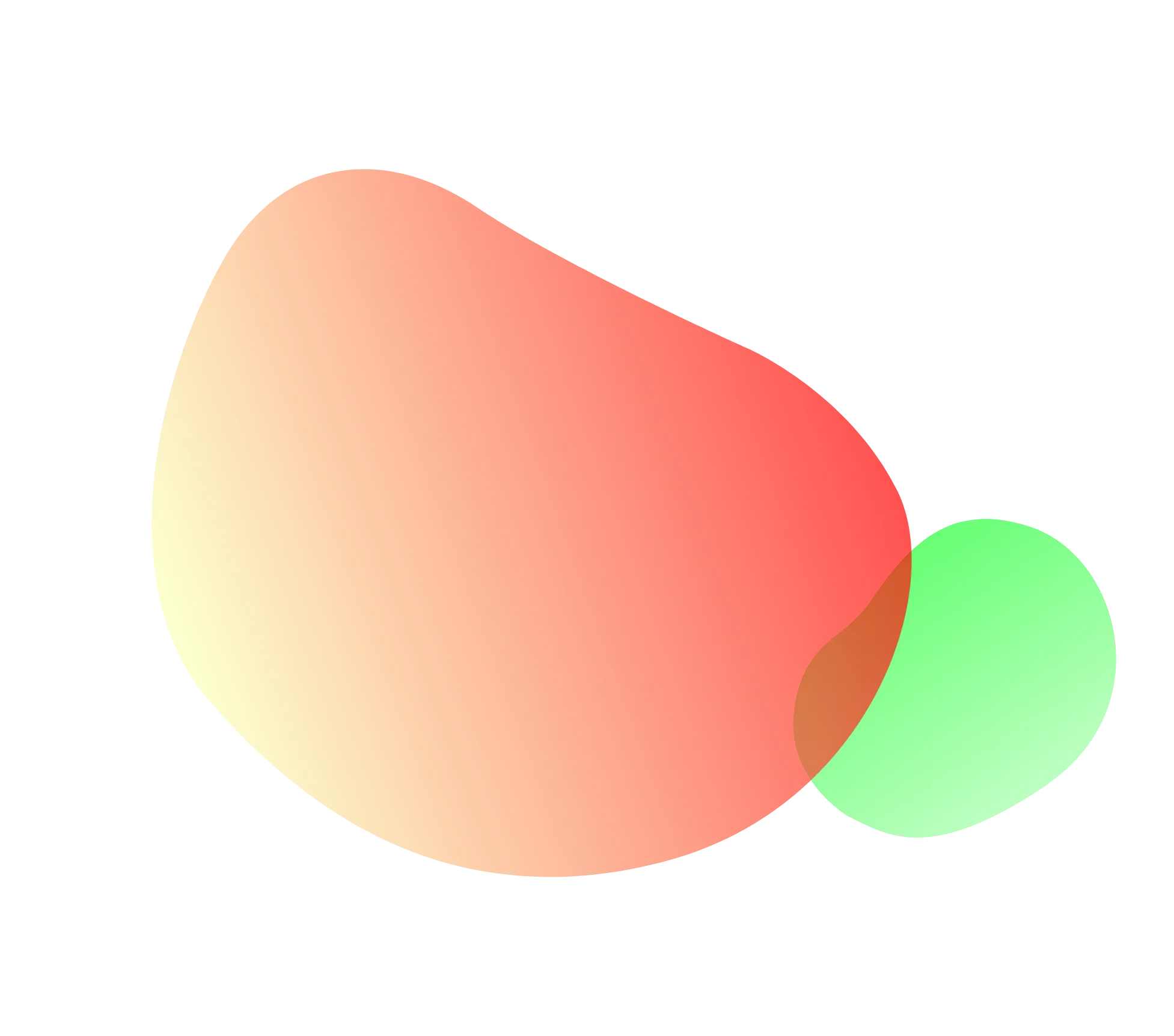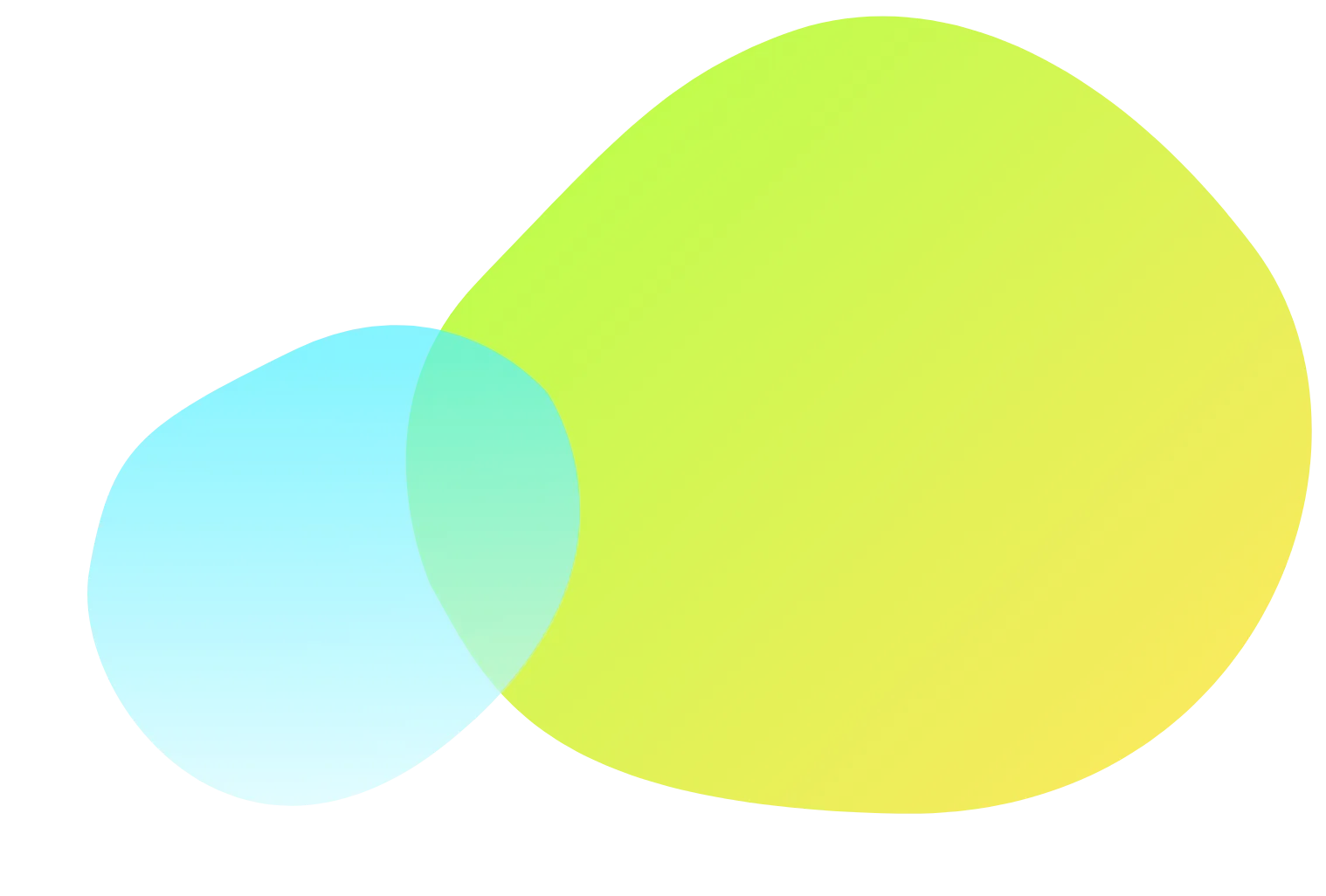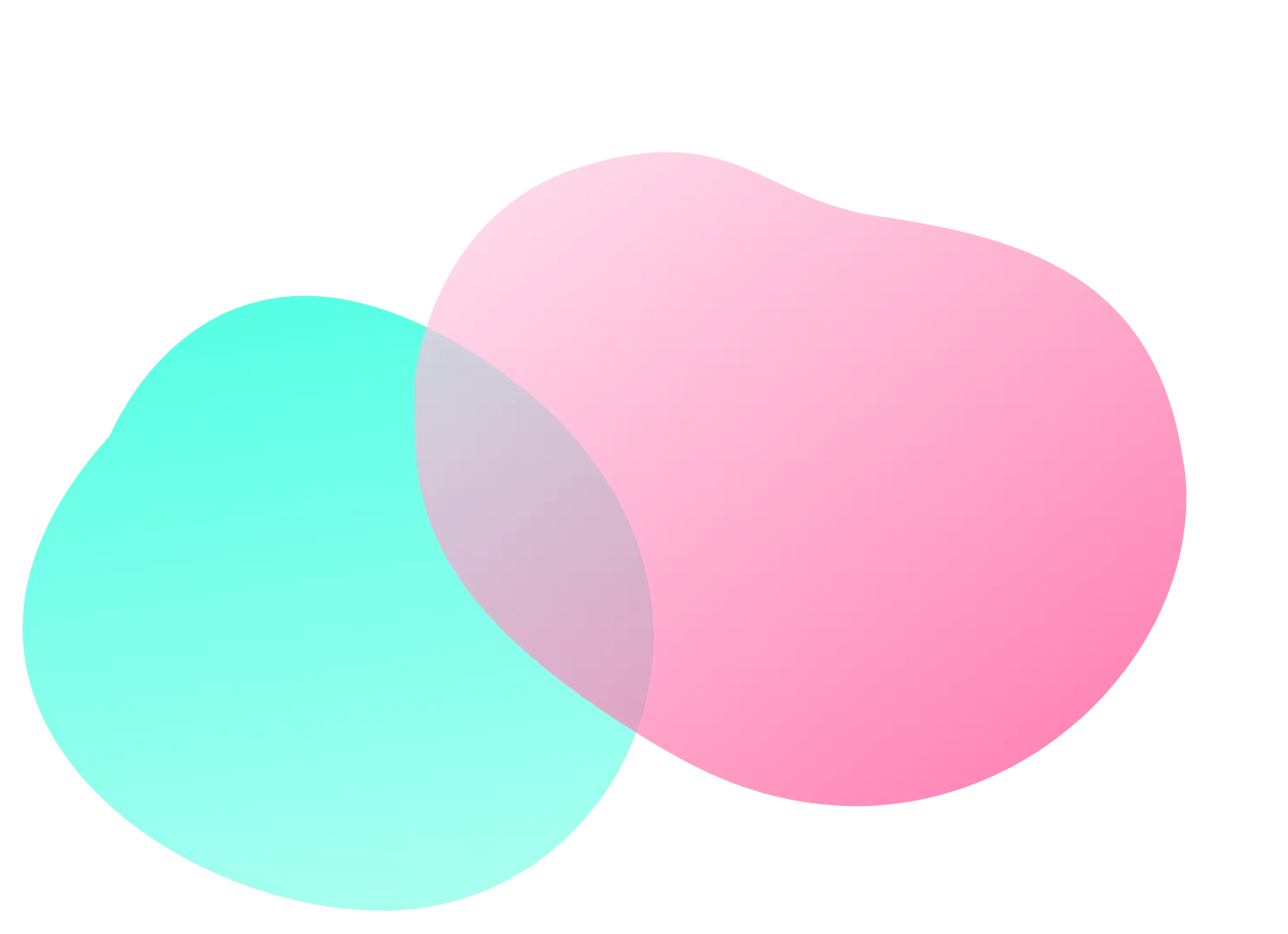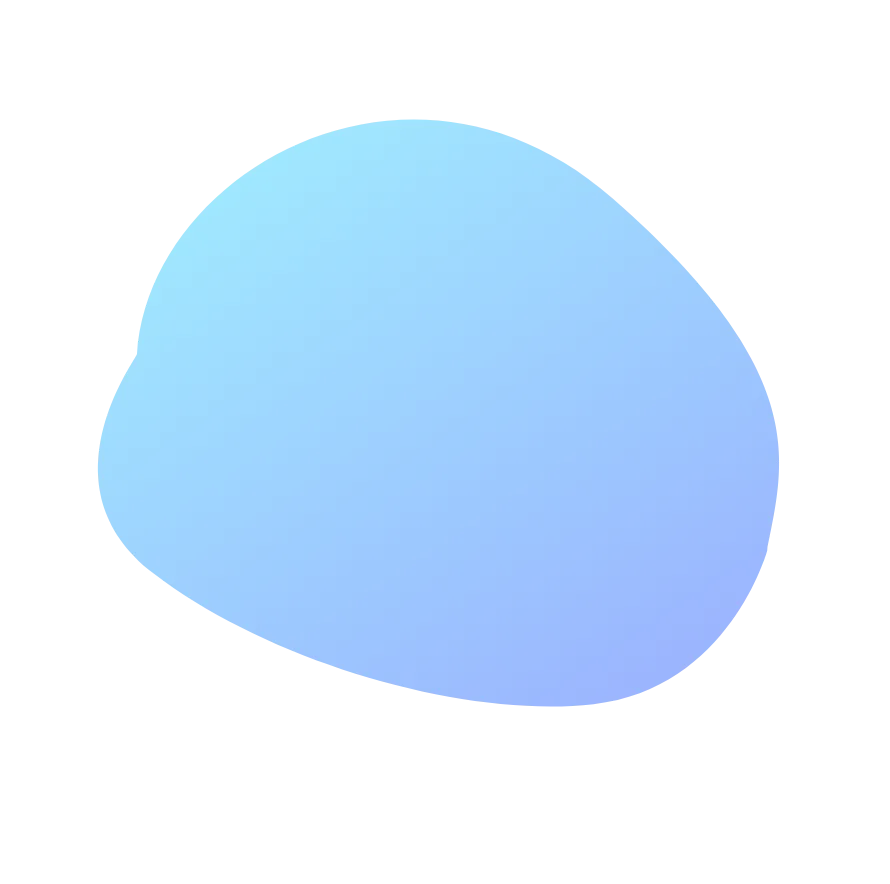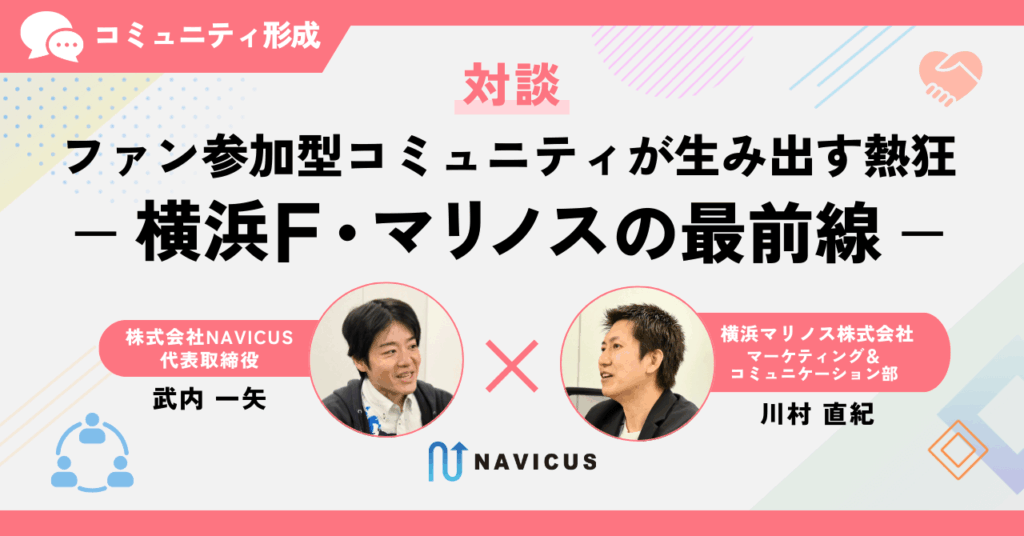
今回は、横浜マリノス株式会社 マーケティング&コミュニケーション部の川村様に、先進的な取り組みを行われているファン・コミュニティ「沸騰プロジェクト」についてお伺いしました。旧来からファンクラブが存在するなかなぜ新しいプロジェクトを立ち上げたのか、どういった工夫が成功の鍵なのか、詳しく伺います。

横浜マリノス株式会社 マーケティング&コミュニケーション部 FRM課 課長
NAVICUS武内(以下、武内):それでは、どうぞよろしくお願いいたします!
横浜マリノス株式会社 川村様(以下、川村):よろしくお願いいたします。
目次
なぜファンクラブと別に「沸騰プロジェクト」を立ち上げたのか?
武内
早速ですが、F・マリノスでは従来からファンクラブがあったなか、「沸騰プロジェクト」という新しいファン・コミュニティも展開されているかと思います。これらが分かれて存在する理由を教えていただけますか?
川村
ファンクラブとコミュニティは、役割が違うと思っています。ファンクラブはトップチームにフォーカスが行きやすく、チームを想うご意見をいただける場になっています。一方、もう一つ上の概念である「クラブとして大きくなるためにはどうしたらいいか」を考えると、別のコミュニティで対話し、違った視点でご意見をいただくのが良いのではないかと考え、立ち上がりました。
武内
そのまま打ち出すと、ファンの方々から違いが理解されづらいようにも感じますが、どう取り組みを広げられたのでしょうか?
川村
沸騰プロジェクトでは、熱量をどう周りに伝えていけるかを大切にしています。まず、F・マリノスではスーパーファンという概念を持っています。F・マリノスを応援してくださる方の中には、指定席に座っている方、ゴール裏で飛び跳ねている方、ゆっくり観戦したい方など様々なファン・サポーターの方がいらっしゃいます。Jリーグも有り難いことに30年を越えてきて、昔はゴール裏で観戦していたけれど今はメインスタンドでゆっくり試合を楽しむといった方も増えてきています。皆さんを一緒くたにして何かに取り組むことは非常に難しいですが、クラブに賛同し同じ目的のため熱量を持って動いてくださる方々と手をつなぎたいと思い、スーパーファンという呼び方を用いて関わらせていただくことになりました。
武内
なるほど。我々NAVICUSメンバーも何度かF・マリノスさんの試合を観戦させていただいていますが、試合後Xに感想を投稿すると、かなりの数のいいねやコメントをいただけます。そういった部分からも、熱量や受け入れる心の強さを感じます。

川村
いろんな方に言っていただきます。以前にじさんじさんとコラボした際も、にじさんじファンの方々がスタジアムへ足を運んでくださり、「右も左も分からない」とSNSで呟いていらっしゃいました。それに対してファン・サポーターの方々がフォローしている姿を垣間見て、ウェルカム精神の強さを感じました。
武内
ファンクラブと沸騰プロジェクトでは、どのぐらい被りがあるんでしょうか?
川村
登録情報を見る限り明確な被りは無く、シーズンチケットやファンクラブに入ってはいないけれど沸騰プロジェクトに参加していただいている方、シーズンチケット会員の方、ファンクラブ会員の方など、様々な形があります。それぞれのカテゴリでクラブと関わりたい、応援したいと思っていただいているのかと思います。
手探りから始まった新コミュニティの試み
武内
沸騰プロジェクト立ち上げの際、他のクラブの取り組みで参考にしたものはありますか?
川村
ありませんでした。クラブに賛同してくださる方がどれだけいるかわからない中だったので、1年間の試験運用から始まりました。クラブからの呼びかけでSNS投稿をするといった取り組みは当時ほとんど無く、SNSではネガティブな反応が出やすい面もあるので、慎重に取り組みました。
沸騰プロジェクト立ち上げ以前は、ファン・サポーターの方からは「F・マリノスはすごい冷たいクラブだ」と言われていました。ただ、沸騰プロジェクトをきっかけに、一緒に皆さんと取り組めるようになり、「クラブが近くなった」と捉えていただける方が増えたと思っています。
武内
NAVICUSでも様々なコミュニティ施策に取り組ませていただいていますが、対話の場づくりをすること自体で歩み寄りを感じていただけることは多いです。接点を増やしたい意思がはっきり伝わることそのものに価値がありますよね。
立ち上げ以降、苦労された点はどういったところでしょうか?
川村
プロジェクトごとの集客や進行が難しかったです。当初は3つの部門「スタジアム沸騰チーム」、「グッズ沸騰チーム」、「クラブ沸騰チーム」に分けてプロジェクトを進行していきましたが、募集を始めたところ「グッズ沸騰チーム」への応募が圧倒的に多かったです。当時自分たちの欲しいグッズが無いと感じる方が多く、とりわけ関与熱が高かったようです。次いで「スタジアム沸騰チーム」への応募が多かったですが、「クラブ沸騰チーム」は取り組みイメージがつきづらく苦戦しました。
武内
確かにグッズの方がイメージがつきやすいですね。プロジェクトから生まれた成功事例では、どういったものがありますか?
川村
最初のグッズ沸騰の時は、アイデアを商品化し、店頭ポップにもプロジェクト発の商品だと書いていただきました。また、アイデアを出してくださった方がアンバサダーになってくれて、積極的に購入を促してくれました。
一番ヒットしたのはトリパラ(チームカラーであるトリコロールの小型パラソル)のパーカーですね。「F・マリノスらしさは欲しいがエンブレムは無くて良い」というご意見があがり、トリパラをモチーフにしたパーカーを作りました。発売初日はあいにく雨天かつニッパツ三ツ沢球技場での試合でしたが、事前に沸騰プロジェクト参加者の方々に予告していたこともあり、クチコミで広まり1時間足らずで完売しました。

武内
ミーティングの進め方についても教えてください。参加者の規模感はどのぐらいでしょうか?いろんな方がいらっしゃるので進行管理も難しそうです。
川村
一回のミーティングで20名前後ですね。5,6班に分けてグループワークをやっていきます。F・マリノスへの関わりの深さによっても目線が異なってくるので、そこも加味してグループ分けしています。また、我々スタッフがファシリテーターとして各班に入らせていただいてます。
新規ファンも古参ファンも巻き込むコミュニティ設計
武内
ファン歴・サポーター歴の違いで深度が異なると思いますが、沸騰プロジェクトではどんな方を対象に取り組まれていますか?
川村
本当に様々な方がいらっしゃいます。目的があくまでクラブを良くすることなので、例えば「どうやったら初回来場が増えますかね?」など、皆さんにおおっぴらに悩みをぶつけることもあります。ただ、長く応援してくださっている方は初回が何十年も前だったりで、当時の気持ちがわからない。逆に年数が浅い方は記憶が新しく、そこにヒントがあったりもします。
武内
コミュニティ施策の場合、新しい方が入って来づらくなるケースも多く見かけますが、そういった課題はないでしょうか。
川村
認識している範囲では無いですね。あくまでクラブを良くするスーパーファンの集まりだという場の位置づけを明確に伝えていますし、ポジティブな場になるようにスタッフも意識しているつもりです。参加いただく皆さまも温かい方が集まっているとも感じています。
武内
沸騰プロジェクト自体の認知獲得は、どういった手段で行っているんでしょうか?
川村
Xでの投稿やリリース発信で目にしていただける部分はありますが、同じような顔ぶれになってしまうと意見が固まってしまうので、幅広い方に来ていただきたいと思っています。初めの頃はプロジェクトの中身が伝わっていませんでしたが、参加者の方々に社員名刺に似た名刺をお配りしていました。その名刺を持ってインフォメーションに行くとグッズと引き換えられる、10%オフになるなどの特典を付けて、プロジェクトの名刺を広めてもらいました。
川村
コミュニティの中の方が新しい人を連れてくる、素晴らしい流れですね!
2025年「リブート」の年へ――さらなる熱狂を目指して
武内
最後に、今後の展望についてもお伺いしたいです。
川村
2025年はリブート(再起動)の一年と捉えており、活動量を増やしていきたいと思っています。リアルミーティングをやった後にしばらく経ってから、ふとした機会に「あんなお話伺ったな」と思い返すことがあります。そういった気付きがクラブの発展につながっていくと実感しています。また自分自身、プロジェクトでご一緒した方とスタジアムでお会いし「あー!」と盛り上がったり、あの時は本当に楽しかったと言っていただけたりすると、関わっていて良かったなと心から思えます。そのためにも、取り組みを増やしていけたらと思っています。
武内
NAVICUSも「明日が楽しみになる居場所をつくる」というミッションを掲げていますが、まさにファン・サポーターの方々にとって、スタジアムで会える方や共有できる体験があることが、代えがたい体験価値になっているんですね。
貴重なお話、ありがとうございました!